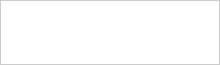特集は「日本社会の転換点 1995年から30年」
今年、2025年はそれまでの日本社会が経験したことのなかった阪神淡路大震災や地下鉄サリン事件が起きた1995年から30年目にあたる。その他にも様々な出来事の起きた1995年は今の日本につながる転換点にあたる。
ジャーナリストで本誌編集委員の竹信三恵子氏は、阪神淡路大震災や地下鉄サリン事件によってそれまでの公共への安心感が失われ、95年は社会の液状化・流動化を印象付けた「不安元年」であり、「失われた30年」の起点であったと指摘する。
95年は北京女性会議が開催され女性運動が盛り上がった年でもあった。会議にも参加した参議院議員の福島みずほ氏は、海外と比べ日本では女性に関する運動の進みが遅く、逆にジェンダーバッシングなどの動きも出てきたと指摘する。また、95年の村山談話を書き替えるような安倍政権の動きは自社さ政権へのリベンジではないかとも語る。
ジャーナリストで衆議院議員の有田芳生氏は地下鉄サリン事件当時のメディアの状況を振り返る。嘘も真も入り混じったオウム一色の報道がなされた状況は、情報が溢れかえる今のネットの原点ではないかと指摘する。
阪神淡路大震災直後から活動を開始し、災害ボランティアのNPO立ち上げた被災地NGO恊働センターの村井雅清氏が当時の活動を語る。95年は「ボランティア元年」と言われるが、その後のボランティアが専門化し一般ボランティアを制限するような傾向に警鐘を鳴らす。
95年に出された日経連の「新時代の日本的経営」は、非正規労働者を雇用の一形態として位置付けた。95年当時はフリーターとして働き、今は貧困、格差の問題に取り組む作家の雨宮処凛氏がこの「失われた30年」を振り返る。そして30年の間に多くの人々が剥奪感を感じる社会となったことでバッシングやヘイトが広がったと指摘する。
95年には沖縄少女暴行事件が起き、沖縄で基地縮小や地位協定見直しの運動が広がった。それを受けて普天間基地返還の合意がなされたが、この30年沖縄への負担は減るどころか、新たな軍備増強が進められている。沖縄国際大学准教授の砂川かおり氏がこの30年の沖縄の動きを解説し、県外の人々も日本の安全保障などについて自分事として考えてほしいと訴える。